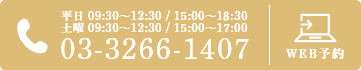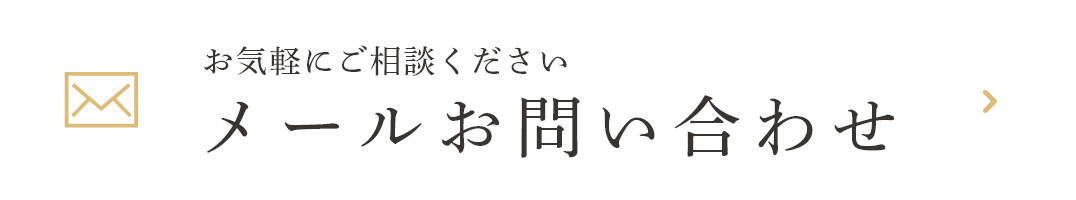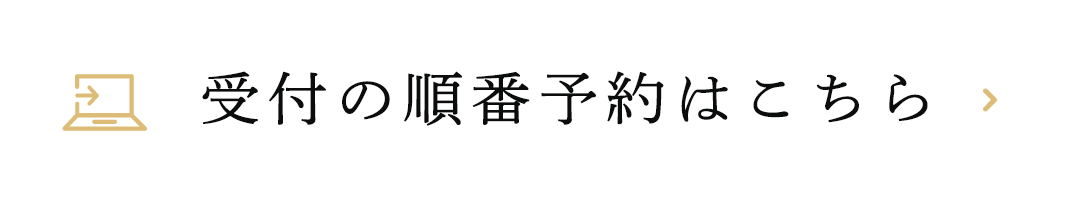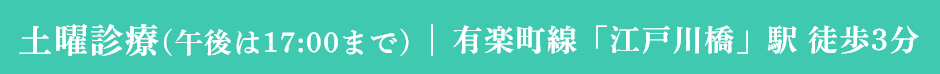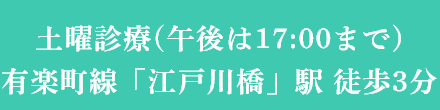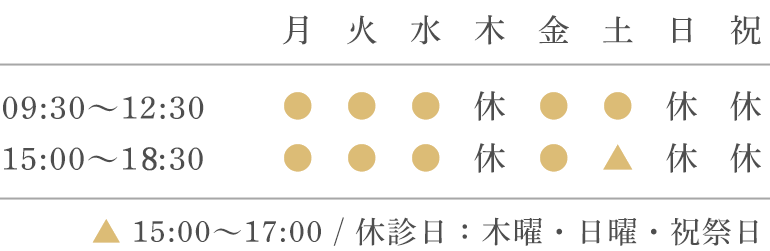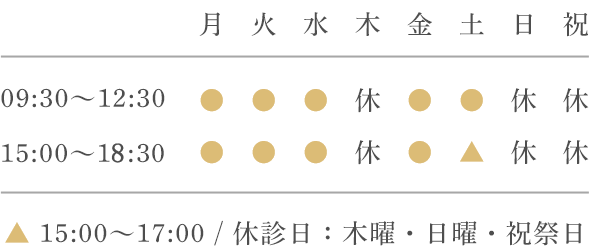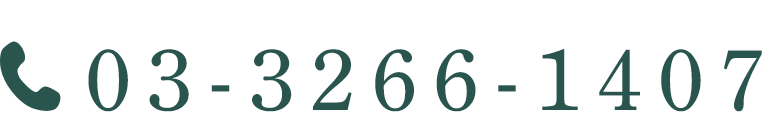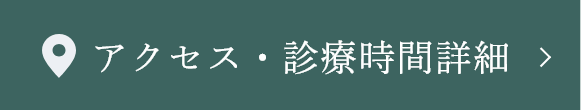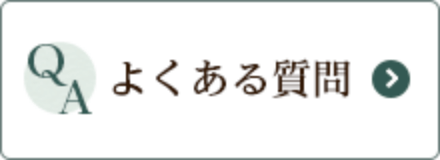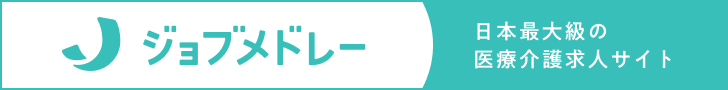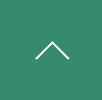足がつる
芍薬甘草湯という漢方薬がありますが、最近有名になってきました。というのは、足などがつるときに非常に有用なので、それが広まったためと思います。葛根湯に次いで皆さんが知っている漢方薬ではないでしょうか。薬局でも「足のつる方によい薬があります」などという宣伝をしばしば見かけます。足などがつるときに内服すると、即時に効果が現れ、漢方薬はじっくり効くというイメージを持っている人が多いので、効果の速さに驚かれる方も多いです。
この処方は2000年ほど前に書かれた『傷寒論』という本に記載されているのですが、古いにもかかわらずよく効きます。現代医学では「足がつる」ときに効く適切な処方がないので、大変重宝されています。その構成薬は、「芍薬」という生薬と「甘草」という生薬2味からなるもので、非常にシンプルな処方です。「芍薬」というのは花としてよく知られるシャクヤクの根です。「芍薬」だけ、あるいは「甘草」だけでも、足のつるのに効果はあるのですが、この二つを同時に使うことでその作用は増強されるのです。昔の人がこの組み合わせを発見したことに驚きを感じます。同じ本、『傷寒論』に桂枝加芍薬湯という漢方薬があります。これは芍薬甘草湯に「桂枝」、「大棗」、「生姜」という生薬が3種加わったもので、芍薬甘草湯がベースになっている薬です。足がつるのに当然効きそうですが、不思議なことにあまり効果はないのです。この辺が漢方薬の使い方の難しさかもしれません。
なぜこうなるかというと、科学的には加えた3つの生薬のどれかに、足のつる効果を邪魔する物質があるためと予想されます。漢方ではどう考えるかというと、料理で考えるとわかりやすいです。白米をおいしい漬物だけで食べるのはなかなか贅沢で、両方のおいしさが引き立って食べられます。しかし、ここにおかずとして他のもの、例えば餃子とかハンバーグがあると、漬物のおいしさは、これらにかくれて半減してしまうと思います。これと同じで芍薬と甘草だけの組み合わせに、他の生薬が入るとその作用がかくれてしまうという風に考えます。
注意してほしいのは、入っている甘草の量が多い漢方薬なので、長期にわたって、1日3回内服する場合は、甘草による副作用に注意が必要です。特に甘草の入った他の漢方薬を他に内服している場合は甘草の量が多くなり、副作用を起こしやすくなります。屯用で1日1-2回程度の内服が無難です。