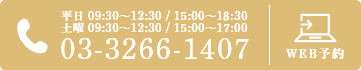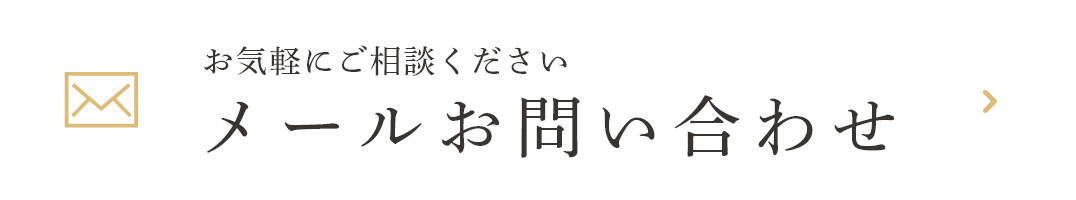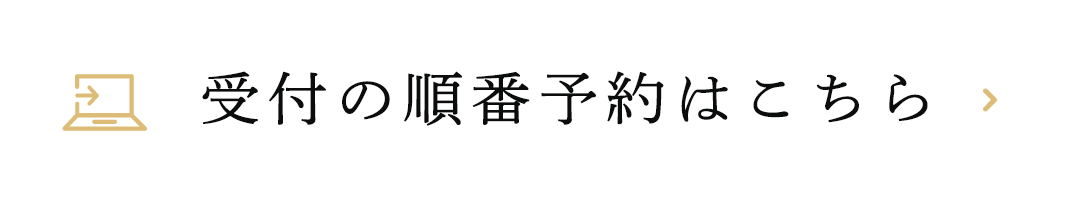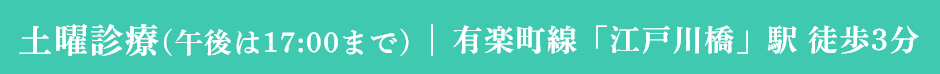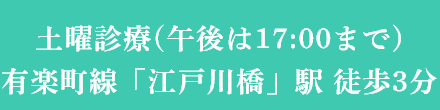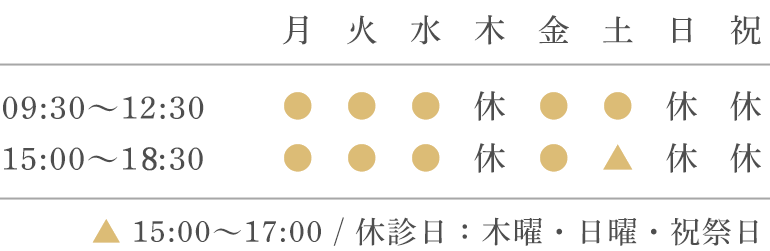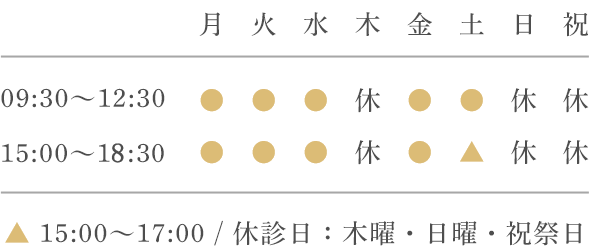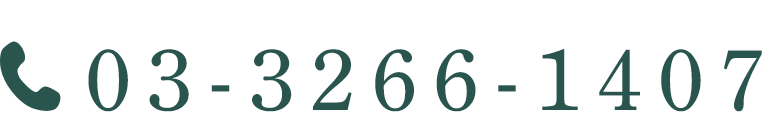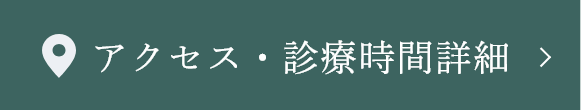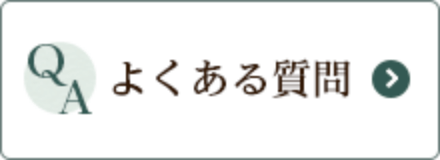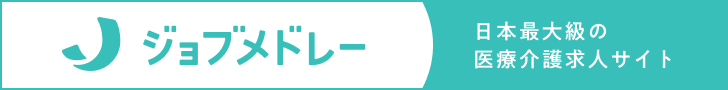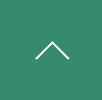甘草(かんぞう)
前々回、ブログに書いた甘草(かんぞう)という生薬のはなしです。偽アルドステロン症をおこして、血圧をあげてしまうという副作用で、有名になってしまいましたが、甘草は漢方薬の中で、使う頻度が一番高い生薬です。ツムラのエキス顆粒では7割の漢方薬に甘草が含まれています。
甘草はマメ科の植物で、日本では自生していません。山菜としても知られるノカンゾウ(ユリ科)やヤブカンゾウ(ススキノキ科)という植物が日本に自生していますが、これは甘草とは全く別物です。
甘草にはどういう効果があるかというと、紀元前に書かれた有名な生薬の本『神農本草経』というのがありますが、これには、生薬を上薬、中薬、下薬の3種類に分類しています。上薬というのは「命を養う薬で、毒性は無く、多量に、長期服用しても人を害することはない。身を軽くし、気力を益す不老長寿の薬」と説明されており、不老長寿に良いもので、副作用とは縁のない薬です。甘草は上薬に分類されているので、「不老長寿に良い薬」になります。それゆえ「副作用など起きるわけがないもの」というのが漢方薬を知っている人の「常識」でした。また、他の漢方薬の作用を「調和する、緩和する」ともいわれています。食品として、醤油、お菓子、リキュールなどの甘味にも使われているので、副作用とは縁のない生薬と私は思っていました。
こういう先入観があったので、もう昔のことですが、甘草に偽アルドステロン症のような副作用があるということに非常に驚きました。実際、頻度は低いですが、たまに経験します。
甘草の効能は、他の生薬と一緒になって甘草はその効果が発揮される場合が多い生薬です。有名なのが、「芍薬甘草湯」です。使ったことがある方も多いのではないでしょうか。足がつった時、「芍薬」単独ではさほど効果はないのですが、ここに甘草を加えて使うと効果が増強し、素晴らしい効果を発揮します。甘草単独では、のどの痛みを止めるというのが有名で、甘草だけを煎じた薬「甘草湯」というのがあり、これもよく効きます。その他にも効能は一応ありますが、他の漢方薬の作用を「調和する、緩和する」感じで、あまり目立つ作用がある生薬ではありません。控えめな薬という感じの生薬です。